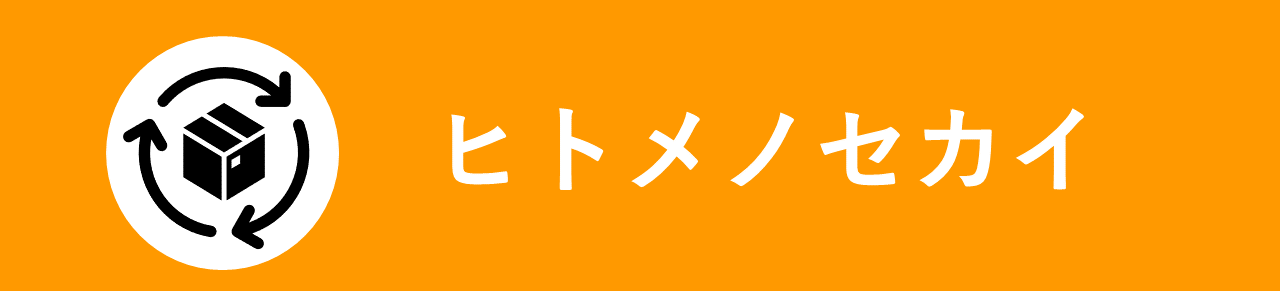この記事の内容:方法序説で紹介されている人生における7つの大切なルールを学ぶ
この記事は本を紹介するための記事です。この記事に書いてあることは本に書いてあることのほんの一部にすぎません。ぜひご自分で読んでみてください!
方法序説について

正式なタイトルは「 理性を正しく導き、学問において真理を探究するための方法の話(方法序説)」。
つまりこの本は、デカルトが考えた世界の真理や、その真理にたどり着くための規則について書かれた本です。
本書は6つの章に分けて書かれているのですが、今回はわかりやすく5部と6部を省いた4つの章について解説したいと思います。
(ちなみに5部はデカルトが公表を控えていた論文について、6部はそれに至る経緯)
1.学問に関するさまざまな考察

1部では、デカルトがどのように本書で述べられている真理や、その規則の考えにたどり着いたかが説明されています。
「良識はこの世でもっとも公平に分け与えられているものである」。
そもそも人間が持ち合わせている一般的な善や悪の判断は誰にでも備わっています。
なのでデカルトによれば、「わたしたちの意見が分かれるのは(略)、わたしたちが思考を異なる道筋で導き、同一のことを考察してはいないことから生じる」のです。
デカルトは子どもの頃から学問に携わってきました。
学業こそが人生に有益であると教えられたからです。
しかし、学業の全課程を終えても彼は学業によってさらなる自身の無知に気づき、多くの疑いや誤りに悩まされました。
結局、学問などは不確実なものだ。確かに学ぶことは大切だが、必ずしも学問が全てではない。
そう考えたデカルトは不確実な学問(文字の学問)に携わるのをやめて、あらためて「真理とはなにか?」という問いに答えを見いだそうとしました。
2.デカルトが探求した方法の主な規則ーその時まで受け入れられてきた事を疑うこと。

30年戦争の時代、デカルトはドイツのある小屋の暖炉にて思索にふけっていました。
そのときにデカルトは、「一人の建築家が請け負って作り上げた建物は、何人もの建築家が、もともと別々の目的で建てられていた古い壁を生かしながら修復につとめた建物よりも、壮麗で整然としている」と考えました。
つまり、一人の良識ある人を前には、いかなる数の人の意見もそれに劣ってしまうということでした。
多数の意見を信じるのではなく、その時まで受け入れられてきた事を疑い、良いものを見極めること。
それが精神を正しく導くための始めの一歩だと考えたデカルトは、そのために4つの規則を挙げました。
1)真理だと証明できるか。
2)できるだけ問題を小さく分割する。
3)単純→複雑の順序を守る。
4)論証が正しいかの確認。
3.道徳上の3つの規則

上記のように精神を導く際は、まだその時点では答えが出ていないので、何が正しく、何が間違っているのかの区別ができません。
そんな時にでも人が幸福に生きられるために、さらにデカルトは道徳上の3つの規則を定めました.
1)自分の国と法律と慣習に従うこと。これは、言い換えれば、自分とともに生きる人々に従って自分を律する事が良いということ。
2)一度決心したら最後までやり通す。たとえばどこかの森で迷った際も、いつも同じ方向に突き進めば、とにかく最後にはどこかにたどり着くから、一つのことを最後までやり通せばいずれかの真理にたどり着くはずだ、ということ。
3)世界を変えるより、自分を変える。 自分の範囲内にあるものは変えられるが、その外にあるものは自分自身の力では変えられないときがある。だから周りではなく、自分を変えた方がいい、という考え。
4.神の存在と人間の魂の存在の証明

では、結局 ”真理”とはいかなるものなのでしょうか。
精神を導くための4つの規則に従えば、疑いのあるものは全て「偽物」のであると判断しなくてはいけません。
そこでデカルトは、いま考えている自分は実際に存在している、と考えました。
これがあの有名な「われ思う。ゆえにわれあり。」ですね。
このようにデカルトは「人間の魂の存在」を証明しました。
そして、「 われ思う。ゆえにわれあり。」 という考え方はある一つの答えにたどり着きます。
それは、「(あるものが)考えるには存在していなくてはならない」ということです。
人は考えるから存在しているし、存在しているから考えることができます。
たとえば、人がリンゴを想像する場合、リンゴは実際に存在しているから想像ができると言ったようにです。
リンゴがもし実際に地球上に存在しないのであれば、誰もリンゴを知っているわけがなく、リンゴがどういうものか”想像”できない、ということになります。
しかし、存在という言葉を使う際に、実際の形の有無は関係ない場合があります。
リンゴの場合だと、リンゴが赤いか、丸いかなどといった外見上の話は関係ありません。
人間が目で見たもの(赤い、丸い)、手で触ったもの(ざらざらしている)など五感で感じたものは、すべてあくまで五感を通して認識したものであり、五感が狂えば目の前にあるリンゴも変化してしまいます。
つまりここで大切なのは、「リンゴがどんなものでもいいけど、自分がリンゴを知っているからそれはどんな形であっても存在するのではないか?」といったようなことです。
これと同じようにデカルトは、形を持たない、概念上の「神の存在」を証明しようとしました。
まずデカルトは「われ思う。ゆえにわれあり」の考えによって自分が存在していると結論づけました。
しかしこれというのはすなわち、疑っているということは未だ自分が不完全であるとデカルトは新たに考えました。
完全なものであるならば、そんな考えをしなくても、「わたしは存在している!」と言えるはずです。
このことからデカルトは人間を「不完全なもの」とし、「不完全がある、ということは完全なものがなくては”不完全”とは言えないではないか」と考えました。
その完全なものこそが神であるとデカルトは言ったのです。
まとめと感想

本書はあくまでもデカルトが導き出した数ある真理のなかの一つとして読者は捉えなければいけません。
デカルトも本書で述べているとおり、本書の目的はデカルトが「自分の理性を正しく導くために従うべき万人向けの方法をここで教えることではなく、どのように自分の理性を導こうと努力したかを見せるだけ」なのです。
ですので、ここでのデカルトの導き出した答えが正しいか、間違っているかは関係ないのです。
「わたしはこういう風に考えました!」というのをデカルトは読者にわかってほしいだけなのです。
この本は1637年に初めて出版されたものではありますが、書いていることは現代の生活に大いに役立つと思います。
「精神を導くための4つの規則」や「道徳上の3つの規則」は自分なりにかなり意訳しましたが、どの規則も現代人が納得できるようなものばかりです。
個人的に、森のたとえは面白いなと感じました。
「自分が想像したゴールではないかもしれないが、どこか一つの方向に突き進めば必ずどこかのゴールにたどり着ける」。
300年ほど前の先人が僕たちにこう言ってくれているのです。こう考えると人間の本質って変わらないものなんだなあと感心しちゃいますね。